|
前夜、ようやく届いたパソコンの設定で、眠るのが遅くなったが、朝5時に目覚めたので、神の思し召しと考え、出発する。ただ、寝不足で、近くの山にと日和たくなる。徐々に目もさえ、快調に走る。ラジオでは、最高気温が30度を超え、真夏日になるところも多く、8月の気温並になると報道していた。乙女の湯を過ぎてからは、今後のために三森山の登山口の桑原橋や嶽山の柿平や山の神を確認しながら進む。柿平は、アルペンガイドに書いている駐車場となる桜の古木は見つかったが、民家の間の取り付き点は、分からなかった。
安川渓谷からは、ダートの林道。落石のありそうな切通しを慎重に進む。途中、又井川林道の起点という表示があり、更に進むとなぜか舗装部分が現れた。再度ダートを走り行き止まりとなる。駐車スペースはUターンのことを考えると、2台がせいぜいという感じだ。何より首をかしげた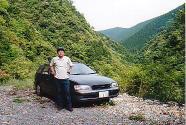 のは、取り付き点が見当たらないことだ。左は崖、前と右は谷で、2ヶ所ある取り付き点が見当たらない。そこで、林道を少しもどり探すが見当たらない。もどって左の崖をよく見ると草に隠れて斜めに登れそうな踏み跡があり、試しに上ると、上部に古いフィックスロープがあった。これだと確信し、車に戻り準備する。 のは、取り付き点が見当たらないことだ。左は崖、前と右は谷で、2ヶ所ある取り付き点が見当たらない。そこで、林道を少しもどり探すが見当たらない。もどって左の崖をよく見ると草に隠れて斜めに登れそうな踏み跡があり、試しに上ると、上部に古いフィックスロープがあった。これだと確信し、車に戻り準備する。
しかし再度挑戦してみると、植林を直登するのかと挑戦するが、急すぎるし、踏み跡もない。右の自然林にも道はない。あきらめて嶽山に変更するかと思った矢先、左に踏み跡程度の道と木に青い紐がテープがわりの感じであるのを見つける。たどっていくと正解のようで、以後、植林帯の急登には、青い紐と低木に赤いテープがあった。
しかし、寝不足と暑さと急登で立ち休憩を繰り返す。時々吹く風が心地よい。植 林には枝打ちした葉が多く、分かりづらいが、何とか分かるのも経験の賜物か。ただし、標高850mを超えると、テープもなくなり、自然林の方に出てしまった。踏み跡があり、すすきの原や馬酔木などの低木で、目の前に法師山や左手に野竹法師への稜線、その奥に大塔山そして右手には三森山が見え、感激する。何枚か写真を撮り、ゴンニャク山が左手上なのを確認し、戻るが野ばらでズボンが破れる。自然林よりの植林帯を上ると、ゴンニャク山山頂であった。展望はなく、紀州わらじの会の標識があり、縦走路には、たくさんのテープがあった。 林には枝打ちした葉が多く、分かりづらいが、何とか分かるのも経験の賜物か。ただし、標高850mを超えると、テープもなくなり、自然林の方に出てしまった。踏み跡があり、すすきの原や馬酔木などの低木で、目の前に法師山や左手に野竹法師への稜線、その奥に大塔山そして右手には三森山が見え、感激する。何枚か写真を撮り、ゴンニャク山が左手上なのを確認し、戻るが野ばらでズボンが破れる。自然林よりの植林帯を上ると、ゴンニャク山山頂であった。展望はなく、紀州わらじの会の標識があり、縦走路には、たくさんのテープがあった。
野竹法師までは、花が多いとの情報だったので、楽しみに進むと、石楠花の花がここそこに咲いていた。満開やら、咲き始めやら様々である。期待通りで大いに満足するが、風で強く揺れるので写真撮影に苦労する。860mの鞍部から上り返すと野竹法師の山頂で三角点や紀州わらじの会の標識やテープ等たくさんあった。しかし展望はなかった。ここで昼食とするが、ばてて、ビールと水ナスの浅漬けと 稲荷寿司だけで済ませ、虫がうるさいので、早々に切り上げる。 稲荷寿司だけで済ませ、虫がうるさいので、早々に切り上げる。
少し迷ったが、縦走路を歩み、南稜を下る。テープが豊富で、途中、石楠花とゴンニャク山、大塔山が見え、写真を撮る。アルペンガイドによると植林との鞍部から100mほど下るとそま道があるというので、テープもないところを下るが急斜面で苦労する。更にそま道がないばかりか自然林でとうとう沢に出る。
地図では、沢沿いに道があるはずなので、ともかく涸れ沢を下る。テープもない道を行くのははじめてで不安である。更に今日は誰にも出会っていない。何とか道をと探すが見つからない。右岸から左岸に渡るようアルペンガイドには記されていたが、分からない。二股となるが、それも5万分の一の地形図では記されていない。2万5千分の一だとどうか確かめてみたいものだ。とうとう水が湧き出しているところに出る。水は飲むとおいしかった。
この先沢下りだと大変なので、前方の踏み跡らしきものを上るが違う。危うく滑りそうになる。仕方なく、沢を下る。最初に美しい小さな滝があった。横を巻けた。更に流木・倒木を避け、苦労して進むと、小屋が右手にあった。つながる道があるはずなので、しめたと思い進むと左上に進む整備された道と沢沿いのかすかな踏み跡。整備された道が正解だと確信し登るが、どんどん高度が高くなり、600mをはるかに超える。しかし、古い土止めもあり、巻き道となるので正解だと思い進むが、どんどん上に行く。
おかしいと思い、戻るべきであったが、「沢沿いに果たして行けるのか、滝があればどうするのか。夫婦滝まで出てしまっても林道に上がれないし、駐車場につながる道はなかったから、朝の上りの道のどこかに合流するのでないか」と推測し、「このままゴンニャク山に登るか、稜線で合流するのでないか。こんなに整備された道だから。迷ったら沢より稜線が鉄則などと、今回は沢沿いに道があるのが分かっていながらへ理屈をこね、上ることにしよう」と判断し、そのまま進む。
暑さと疲労としゃりばて気味で、休憩を繰り返し、水分補給をし、冷たいたらみのいよかんゼリーを食べる。しかし、だんだん道は悪くなり、藪が出てきて、踏み跡も薄くなる。野ばらで半そでの手が傷だらけとなる。とうとう有刺鉄線がでてきて、アルペンガイドの有刺鉄線のことだが、そうするとこれが本当のゴンニャク山へのルートなのかと考えてしまう。見晴らしのよいところで地形図で確認するが、沢からゴンニャク山方向に北に上っているのに間違いない。
しかし、有刺鉄線を無理やり越えるといよいよ藪は深くなり、標高800mを越え、朝感激したゴンニャク山手前のすすきの原に出そうだが、藪で道は分からず行けそうにない。途中、藪でめがねが飛ばされたり、古木が腐り、つかまり折れて滑り落ちそうになるなど、さんざん苦労する。考えた末、仕方なく、小屋まで戻り、沢沿いに行くことにする。ただ、それでも道があるか不安で、遭難という文字さえ頭をよぎる。
更に、下るとなると踏み跡がさらに薄く見え、上部では行きつ戻りつ不安一杯で下るが、どうにか沢に降り立つ。途中、疲れで足元ふらふらで滑ったり、めがねが藪に飛ばされ、倒木の根元に入り込み、探すのに苦労するなど惨々であった。沢の水でのどを潤し、顔や傷だらけの手を洗い、右岸の薄い踏み跡を歩く。すると、ほどなくはっきりしたそま道となり、これが正解の道だと確信し安堵する。
草が茂り、細く歩きにくいところもあり路肩が崩れ危うく滑り落ちそうになったが、20分ほどで、ひょっこり林道突き当りのところに出た。取り付き点も草で隠れて見えなかっただけである。やはりテープもない道は、私にはまだ無理なのかもしれない。疲労困憊で記念撮影し、反省多くして帰路に着く。乙女の湯でゴンニャク山の由来を聞くが知らなかった。それにしても温泉で見ると手だけでなく体中、傷だらけだ。
折角の機会なので、和歌山まで携帯のauの圏外確認しながら走る。R311沿いと椿山ダムからのR424が通じたが、しらまの里を越えるとしばらく圏外であった。反省の多い登山であったが、勉強になった。
HOMEへ
|